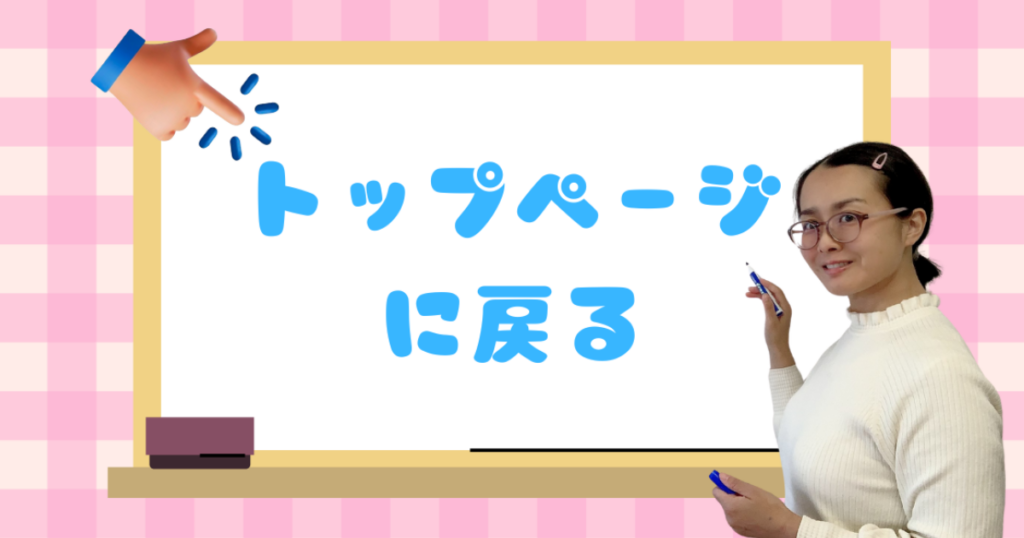子供が自己選択・自己決定をする材料である「学習」する機会を大人が奪わないで!

以前、介護の仕事をしながら学習支援の教室でアルバイトをしていた時に、講師仲間から、
「勉強する気のない人の学習を、どうやって支援すれば良いのか分からない。」
と相談を受けたことがあります。
学生アルバイトさんたちは、子供のお話を聞いたり一緒に遊んだり、一生懸命やっているのですが、子供たちの方から
「ここに何をしに来ているのか分からない。」
という声が上がるようになり、だんだんと休む人の数が増えてきました。
勉強する気がないのに、勉強をしない場所だと通う意味が分からなくなるというジレンマに、講師の方々は大変悩んでいました。
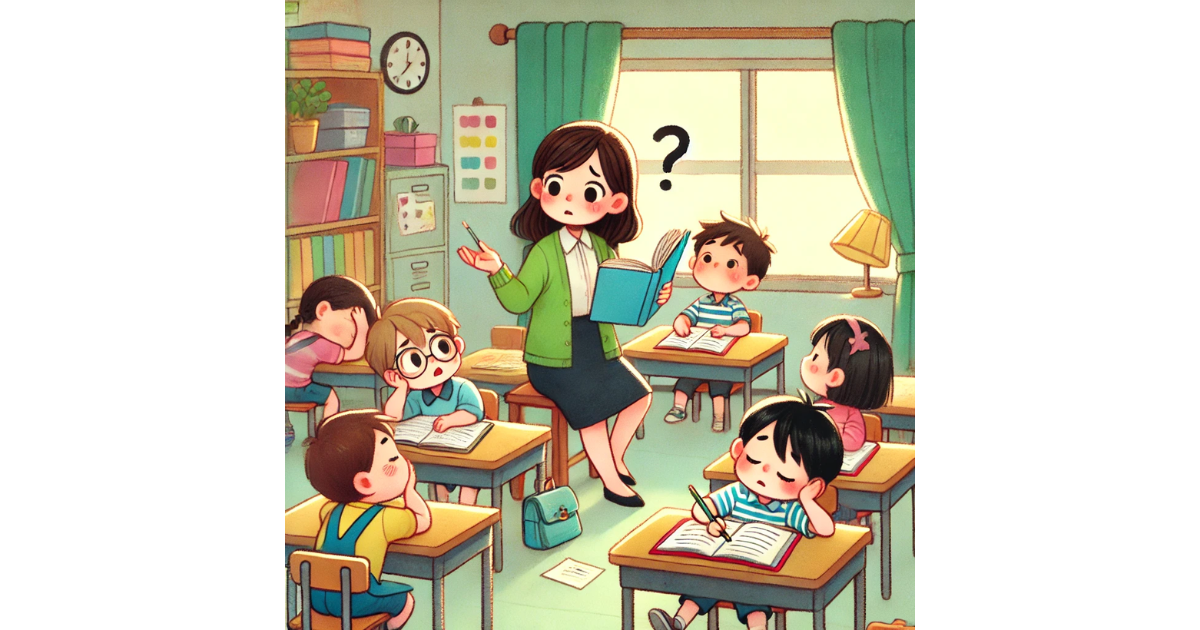
その後、その「ジレンマ」を解決すべく、私は本格的に教育の仕事に従事するようになりました。
コーチングやカウンセリングを学び続けながら、通信高校サポート校や適応指導教室で働いて、500人以上の不登校の生徒たちと対話をしたり授業を受け持ったりする中で、だんだんと自分の中で答のようなものが見えてきた気がするので、こちらの記事にシェアさせていただきたいと思います。
もくじ
①学習に対する興味を持っていない子供はいない
②子供の興味を大人が奪わないで!
③学習は自己選択・自己決定をする判断材料となる
④知識を押し付けるのではなくて、知りたい気持ちを引き出すという対話法
①学習に対する興味を持っていない子供はいない
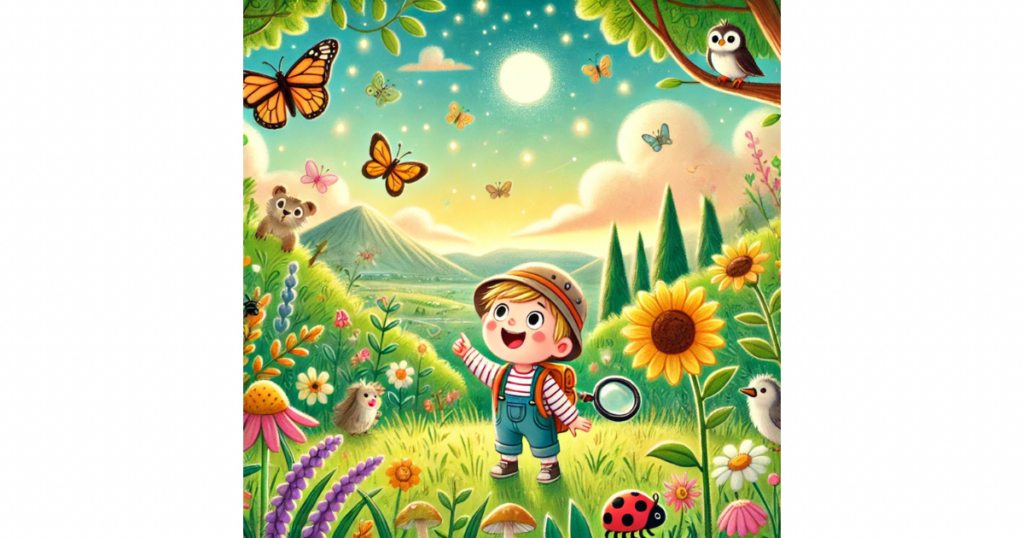
生まれた時、子供は皆まっさらな状態です。
訳の分からないところに突然意識を持って放り出され、その中で生きるために必死で周りの全てを自分に吸収してその場に適応しようとします。
母乳を飲んだら飢えが止まることを学び、排泄したら腹部の不快感がなくなることを学びます。
活動範囲を広げるために、自ら起き上がって移動することを学び、転ぶと痛いことを学びます。
私たちは、自分がよりよく生きるために、生まれた瞬間から必死で学んでいるのです。
幼児になると、どんどん興味の対象が広がってきます。
「どうして空は青いの?」
「世界の果てはどこにあるの?」
「これは何の材料からできているの?」
「人間は死んだらどうなるの?」
気になったことは全て大人に質問をするようになります。
その時の大人の答で納得することもあれば、もっと知りたいと思って本を読むこともあります。
まずは、「疑問を持つ」ということが、知識の入り口に立つきっかけになるのです。
②子供の興味を大人が奪わないで!

しかし、それに対して大人の対応はどうなのでしょうか?
上記の質問に、その場で答えられる大人はどのくらいいるのでしょうか?
中には、「そういうものなんだ。そのうち学校で習う。」などと、答えることを面倒くさがって適当にあしらってしまう大人も少なからずいると思います。
そうすると、子供は大人の顔色を伺うので、
「あまりきかない方がいいのかな。」
となり、自らの興味を心の中に封印してしまうことにもなります。
せっかく子供が興味を持って学びたいと思っている芽を、大人が摘んでしまっているのではないでしょうか。
大変、もったいないことだと思います。
また、ここで「知識を押し付ける」ことも逆効果です。
子供にとってまだ知らない言葉がたくさんある中で、ベラベラとウンチクを話すのはどうでしょうか。
そして、子供が興味を持った瞬間を待っていましたとばかりに、大人が読んでほしい本を押し付けたり教育番組を見せたり来ることもどうでしょうか。
子供は、質問を通して、大人と「発見の感動」を共有し、コミュニケーションを取りたいだけなのです。
「いいところに気がついたね!」
「ヘェ〜そうなんだ!面白いね!」
と、子供の目線で一緒に会話を楽しみたいものです。
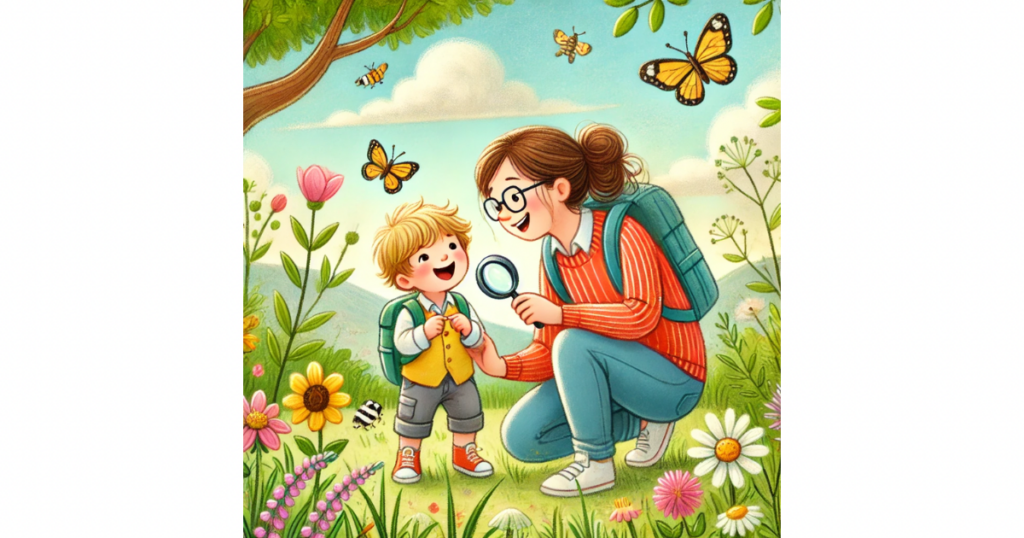
ただ、子どもたちは、学校に行くことで純粋な学ぶ興味を少しずつ忘れます。
時間になったら登下校の集合場所に行く、チャイムがなったら着席していないといけない、私語をしたら注意される、今までにはなかった「学校教育」を押し付けられることで、ストレスが蓄積されていくのです。
また、人間関係が非常に面倒くさくなります。
誰々ちゃんが悪口言っただの、誰々ちゃんと口きくのやめようだの、自分の興味と関係ない会話を周りからきいて精神的苦痛を味わうことになります。
自分の一年生の時のことを思い出すにつけ、あの頃には絶対に戻りたくないと切に思います。
(その頃から、将来は子供が生きやすい学び場を作りたいと考えていました。学校なんか大嫌いです。)
そんなくだらないことでストレスを溜めて、子供が生きている中で、「興味」はますます心の奥に封じ込められていきます。
さて、話を学習支援の場に戻します。
学習支援の場には、学校に行きづらい子供や学習に対する興味をなくした子供、家庭で学習する環境を与えられない子供が数多くやってきます。
自らの「知りたいと思う興味」を奥底に封印した子供たちには、「興味を引き出す」関わり方をしていきたいところです。
しかし、先生たちは自分が「優秀」で「恵まれた環境で育った」人が多く、
「なぜ、子供が勉強しないのか。」
「なぜ、こんなに簡単なことが分からないのか。」
と、本気で思っている人が多いのです。
すると、子供の会話にただついていくだけになってしまったり、関わり方が分からなくて子供に対して距離を置こうとしてしまったりといった接し方になってしまいます。
それでは、子供たちからしたら「真のニーズ」を満たされていないので、次第に来る気が無くなってしまうのも仕方がないのです。
「真のニーズ」は人それぞれですが、学習支援の場に自ら来るということは、
「自分が変わるきっかけをここでつかめるかもしれない。」
「自分の本当に知りたかったことを、ここで知ることができるかもしれない。」
という期待があるからです。
これらの「ニーズ」を把握しないまま時間だけズルズル過ぎるのを待っていたり、「子供に合わせる」という大義名分のもと子供の会話に引っ張られ続けるだけだったりすることは、
「子供から学ぶきっかけを奪っている」
ことと同じことだと私は考えるのです。
③学習は自己選択・自己決定をする判断材料となる
「勉強する気がない子供は、教室に来るだけでいい。」
確かに、健康面だけで考えれば、家にずっと引きこもっているだけよりは、少しでも外に出て親以外の大人と触れ合うことは子供の成長にとって刺激になることでしょう。
学習は生活習慣が整ってから。
これも一つの考え方です。
その上で私が言いたいのは、
「大人との触れ合いの中で、学習に興味を持つきっかけを引き出してほしい。」
ということなのです。
ただおしゃべりするだけでもなく、ただカードゲームやボードゲームをするだけでもなく、
目的意識を持って、活動を展開してほしいのです。
そして、自習時間はただドリルをやらせていればいいわけではありません。
そもそも、学習に支援が必要な子供は、自分でドリルを進めることなんて出来ない子供の方が多いので、お話をしながら一緒に進めていく必要があります。
それぞれの活動の中での「大人との関わり」を通して、子供のニーズを拾い、そのニーズに焦点を合わせて会話をリードしてほしいのです。
学習支援の場で、学習に対するきっかけを見出せなかったら、子供はどうなってしまうのでしょう?
通信高校には、九九が出来ない生徒、漢字を知らない生徒、太陽は東から昇るといった一般常識を知らない生徒は本当にたくさんいました。
こうした子供たちがそのままの知識で居続けたら、社会に出る時にどのくらいの選択肢があるのでしょうか。

勉強ができることが全てではありませんが、出来ないよりは少しでも出来た方が選択肢は広がっていくものです。
また、実生活において、身近なところだと「食事」に関して、適切な知識を持っていないと、そのまま健康を害することにつながっていきます。
大人が理由も伝えずにただ「バランスよく野菜もしっかり食べなさい。」と押し付けても、子供がその理由をしっかり理解していないと、
「イヤイヤ食べる」
「大人が言うから食べる」
ということになってしまい、いざ自分が大人になりうるさくいう保護者が周りにいなくなった途端に、
「私は自由だ」
と勘違いし、今まで抑圧されていた分、自分の好きなもの(お肉や甘いもの)だけをたくさん食べて、糖尿病などの生活習慣病になってしまうのです。
同じ野菜を食べるにしても、「自ら選んで食べる」ことと「強制されて食べる」ことでは、天と地との差が出てしまうということです。
知識は、子供の未来を作ります。
本当に子供の「意志」を尊重したいのであれば、まずは子供の「興味」を引き出して自ら知識を得たいという気持ちにさせて、その上で様々な知識を教えていくことが必要なのです。
④知識を押し付けるのではなくて、知りたい気持ちを引き出すという対話法

では、どのように子供の「興味」を引き出して知識の入り口に立てるようにサポートすれば良いのでしょうか。
実際にあった事例を紹介させて頂きます。
M君の事例
教室に来ても、テキストを出さずにただフラフラ歩き回っていることが多かった小学3年生のM君のお話です。
ある日、M君が辞書を片手に歩いているところを呼び止めて、
「うんこって、いつも言ってるけどさ、先生に怒られないように、他にもっといい呼び方がないか調べてみようよ。」
と声を掛けてみました。
うんこという言葉に反応したM君は、持っていた辞書で調べ始めました。
「くそとか載ってますね。」
と笑いながら言うM君。
「じゃあさ、くそがどうやって出来るか知ってる?」
と質問してみると、
「え、むしろ知りたいです。」
というので、消化の仕組みについて、体の仕組みをホワイトボードに描いて説明を始めました。
すると、「メモするんで待ってください。」と自ら筆記用具を取り出して、ノートに写し始めたのです。
説明の中で、アミラーゼやペプシンなどの酵素の話を盛り込んだり、消化器系の働きと位置説明なども同時に行なっていきました。
食べたものがうんこになるまで、一通り解説するとM君は、
「もっと知りたいです!明日もお話を聞きに来ていいですか?」
と目を輝かせながら言って帰っていきました。
それからは、私と会うたびに、
「先生、理科やりましょうよ。」
と声を掛けてくれるようになり、自らも色んな本を読んで勉強するようになり、学習タイム中は集中して自分の好きな科目の勉強をするようになりました。
ちょうど、私が他の学校で生物の集団授業をしていた頃で、「うんこの話なら子供も好きだろ」と思って、小学生向けにわかりやすく解説を試みたのですが、思ったよりも本人にとってハマったのです。
もちろん、相手の見極めも重要ですが、彼はもともと知識をもっと知りたいタイプの顔をしているのに、机に向かって本を開くことが得意ではなかったために、なかなか知識を得ることが出来なかったのです。
大人が「本人の知識欲を満たせるような声かけ・誘導をする」ことで、うまくいった事例です。
子供にもよるかもしれませんが、まずは、
「子供の好きなことに関して、話を合わせて信頼を得る。」
ことがとても重要で、子供が、
「この大人は味方だ、自分を否定しないから信用できる。」
「共通点がたくさんあるから話が合いそう。」
と自分に対して思うようにすることが大切です。
否定され続けてきた子供は、本当の自分をさらけ出すことに、非常に臆病になっているため、「知識に対する興味」を外に出すことを怖がっています。
まずは安心させてあげることで、子供はいつの間にか「本当の自分」を出してくれるようになります。
学習タイムだからと言って、
「座っていなさい。」
「静かにしていなさい。」
と、子供の行動を否定し続けるばかりの教育で、子供が「本当の自分」を出すわけがありません。
「もう小学生でしょ?」
「保育園児じゃないんだから。」
たまに、このように怒る先生もいらっしゃいます。
これは私の持論ですが、年齢による教育の画一化は先生にとって「楽だから」行なっているとしか思えません。
生まれた場所も育ってきた環境も、遺伝子も違う。
子供の「標準」なんて、あくまでも「平均値」に他ならず、その価値基準は大人たちが決めたもの。
その「平均値」から外れてしまうと、他にどんなに才能を持っていても「劣っている」と決めつけられてしまうのが、今の世の中です。
親ですら、その価値基準に縛られるので、自分の子供と周りの子供と比較して自分を卑下しますが、それもいけない。
「保育園児ではないんだから。」
「あなた、幾つなの?」
なんて、ナンセンス。
成長は人によって違うのです!
1人1人の成長に合わせて、その段階に即した教育を行うことが、本来ではないでしょうか?
それが「先生」という職業であると、私は思います。
正直、保育園の先生の方が生徒の扱いはうまいですね。
生徒の興味を引き出しながら、自分で行動できるように声かけをしています。
授業中に生徒が寝ていたら、起きたくなるようにするんです。
例えば、笑いをとってみたり、全員に体を動かすように伝えたりして、生徒が自ら興味を持って「寝たい」より「起きたい」ことを選択するように環境を整えます。
生徒が「起きたい」という選択をしたら、今度は生徒の能力に合わせた作業を提案します。
学校ならともかくですが、学習支援を必要としている子供たちが多く集まる教室では、生徒1人1人に合わせたサポートが必要になります。
生徒を決して否定せず、それぞれの「本来の姿」を認め、心の中に眠っている「興味」を引き出す。
その興味を持ったことに対して「質問」を投げかけて何でか知りたくなるように仕向ける。
「質問」をすることで、脳は空白になります。
脳は空白を嫌うため、それを埋めるために「答を知りたい」と思うのです。
そして、生徒のレベルに合わせて噛み砕いて何でも嫌がらずに教えていく。
途中で、生徒がチャチャを入れてきても、それに一度は乗っかっていつの間にか話を先生のペースに持っていく。
まずは先生が生徒に合わせていれば、生徒と先生の波長がだんだん合ってきて、今度はいつの間にか生徒が先生のペースについてくることが出来ます。
これを、コーチングの考え方で「リーディング」と言います。
ぜひ、生徒様の興味を引き出すテクニックとして、使ってみてはいかがでしょうか。
まとめ
・生徒の言動を否定せずに、共通点を多く提示して信頼を得る。
・生徒が何かに興味を持ったら、「質問」を投げかけて答を知りたいと思わせる。
・生徒が知りたいことに対し、生徒のレベルに合わせて噛み砕いて何でも教える。
・あくまで、生徒個人に焦点を置いて、生徒のペースに乗っかって会話を進めていく。(ペーシング)
・生徒を先生のお話の世界にリードする。(リーディング)
今回の場面の想定は、あくまでも少人数制の個別学習中になります。
一度に複数の生徒に対しては難しいと感じる先生もいらっしゃると思います。
そういう時は、私はその集団の中に紛れます。
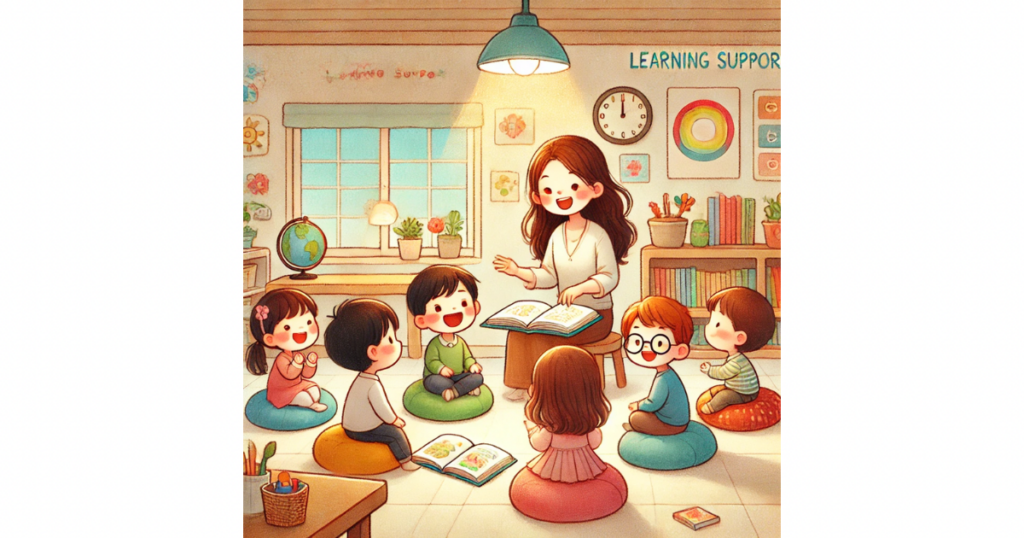
もし、集団でワイワイガヤガヤを始めたら、「静かに!」とするのではなく、先生もワイワイに入ってしまいます。
生徒よりも先生の方がお話も得意だし、知識も深いわけなので、生徒たちはいつの間にか先生のお話に聞き入ります。
生徒同士がそれまでお話をしていたのであれば、そのお話に入り込み、その中から生徒が興味を持っていることをピックアップして、「質問」を投げかけます。
そこから、授業を展開していくのです。
本来、子供はあらゆることに対して興味を持っているもので、興味から知り得た内容は自分の行動を決定する判断材料になります。
是非とも、生徒に知識の入り口に立ってもらい、楽しく学習できるように、大人がサポートしていけると良いなと思うとともに、大人も一緒になって学ぶ過程を楽しんでいけたらと思います。