大人になった、元・小学生湯灌師の話
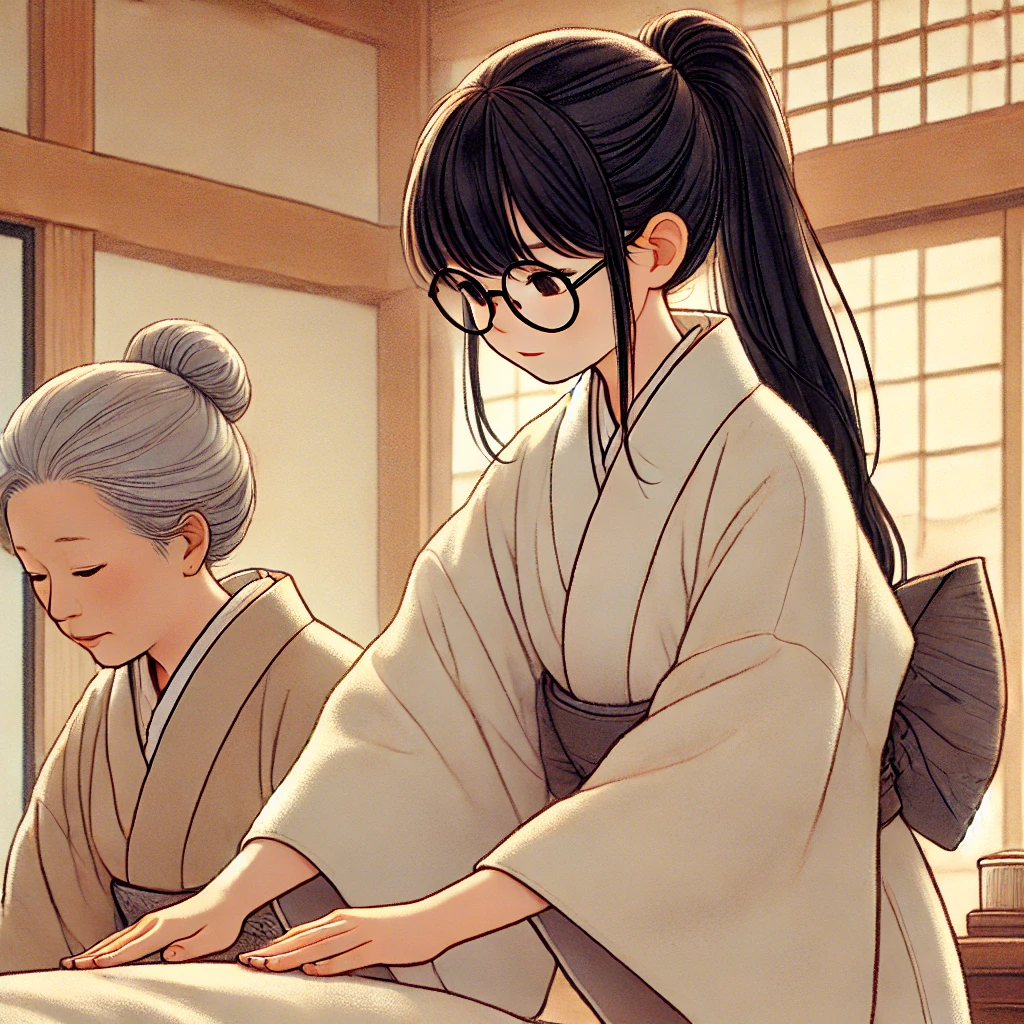
家業の「湯灌」を手伝っていた小学生の私
私は、小学生の頃から
母が立ち上げた「湯灌代行業」の会社を
手伝ってきました。
母と一緒に
色々な亡くなった方の家や葬儀会館に行き、
多くのご遺体のお身体を清めさせて頂き、
仏衣やお洋服を着て頂き、
柩の中に入れて装飾をさせて頂きました。
色んなご遺体がありました。
床ずれだらけのおばあちゃん、
身体の大きなおじいちゃん、
ナイフで滅多刺しにされた若い女性、
事故で身体が原型を留めていない方、
様々なご遺体にお別れの準備をほどこし、
ご遺族の悲しみを
少しでもケアさせて頂けるように
母と一緒にお仕事をさせて頂きました。
久しぶりの「納棺」の仕事
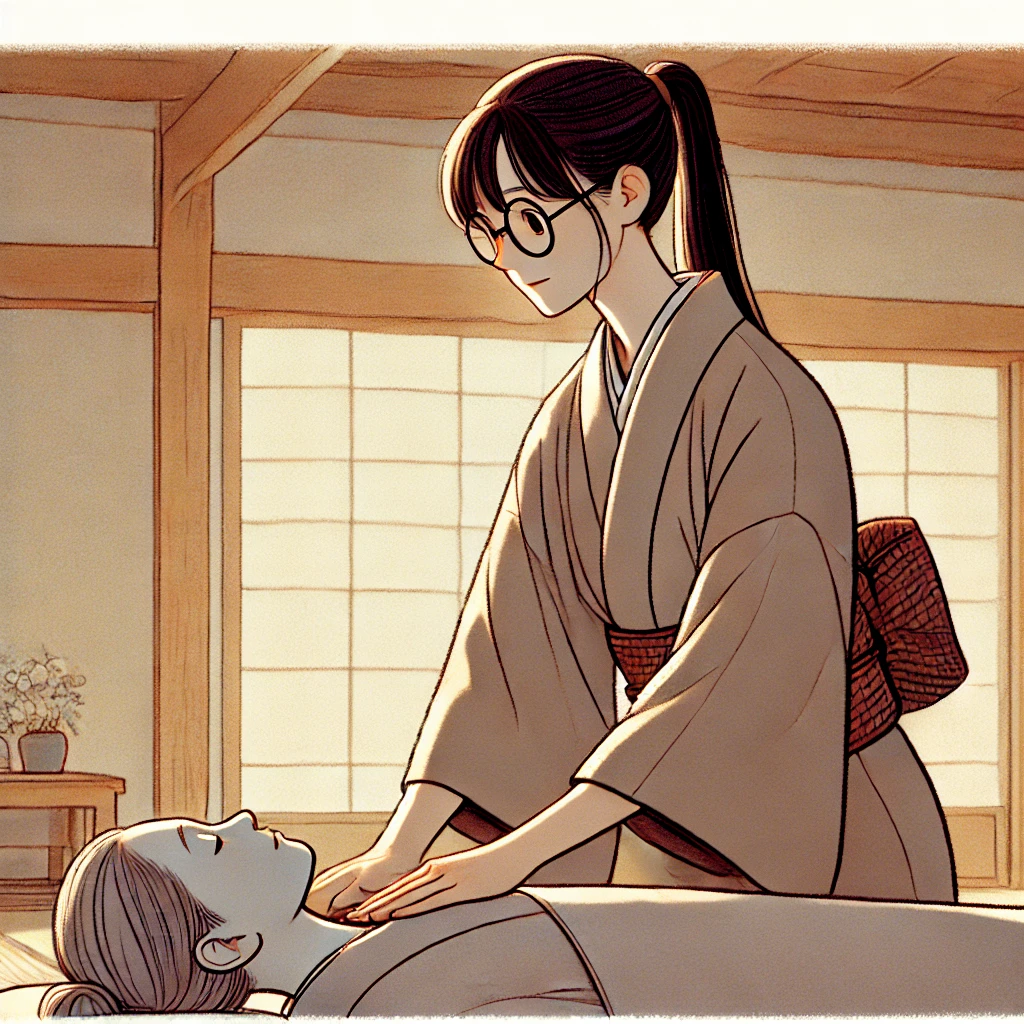
先週は、
約22年振りに
納棺をお手伝いさせて頂きました!
お世話になった方が亡くなり、
母と私の強い希望で
今回お手伝いさせて頂く流れとなりました。
現職の湯灌師が
処置と清拭と仏衣着せ替えを行ったところから
引き継ぎ、
故人に似合う大島の着物と帯を
着せて差し上げ、
メイクとヘアメイクをほどこし、
母と2人で柩の中に入れて装飾をしました。
死後1週間もすると
死後硬直がとけるため、
着替えはしやすいけれど
お顔をしっかり固定しないと
口が勝手に開いてしまいます。
小学校の頃から培った納棺技術と
長年の介護技術で納棺までつつがなく進行し、
母と2人でご遺体を軽々担いで柩へ、
と思いきや、
私も母も現場離れてしばらく経っているので、
なかなか身体が持ち上がらない!Σ(゚д゚;)
70歳の母はともかく私もかよ!
と、
日々続けることの大切さを実感しました。
故人のお身内の方もお忙しく、
湯灌師さんたちも雪の影響で仕事が遅れて
慌ただしく帰ってしまった後だったので、
(最初は、
勉強のために見学させてほしいと
言われていました。)
広いお家に私と母とご遺体がポツン。
「やるしかねぇ!」
と、5回目くらいのトライで
ようやく身体が持ち上がり、
お柩の中に入れて差し上げることが出来ました。
コンプレックスになっていた他の子供とは違う経験

小学校の頃は
母の仕事をほこらしく思っていたけれど、
中学高校になると、
周りと違う経験を持つ私が逆にコンプレックスになっていました。
なんで、うちは普通じゃないのかと
自分のコミュ障を親のせいにしたこともありました。
小さい時から
亡くなった方の話や宗教の話に囲まれて
暮らしていたため、
周りの人と話がなかなか合わなかったのです。
20歳の時に家出して以来、
20年以上経って、
久しぶりに母の一緒に仕事をして、
母は素晴らしい仕事をして
私に高い授業料払って学校行かせてくれたんだと
改めて感じました。
そして、
私の技術は人のためになることを
しみじみ感じました。
遺族の方にとても感謝され、
その後も
「横浜の娘さんにまたお会いしたいです」
と、
毎日のように母に連絡をくださるそうです。
自分を認めて、自分に合う活動をしていく

私は私に合う場所に生まれて育ち、
私に合った経験を今までして来ました。
私に合う活動をすることで、
非常に人に感謝されるのです。
世の中の役に立つことができるのです。
ないものを欲しがるのではなく、
自分にあるものを財産だと思えば、
私の人生は非常に豊かで、
私自身が非常に誇らしい人財なのだなぁ…
この実感を、
私は不登校や引きこもりの人たちに
どんどん伝えていきたいと思います。
私の授業は、
世の中や生活に本当に役立つ構成で
展開していきます。
今の職場では残すところ3回の授業になりました。
社会(主に歴史・倫理)や理科(生物化学)の授業も
それなりに需要があり得意としてるけど、
最後の授業はあえての
「小中学生が知っておきたい介護の基本」
にしました。
学校に行かなくても、
今、自分ができること、
家族のために役立つことを学んで
実践して自信をつけて
将来につなげるきっかけになればよい、
そう考えています。
どんな経験も、
それは自分の財産。
子供たちと未来を繋げるために
私はどんどん自分の経験から
授業を行っていきます!

↑↑↑ほほ先生の過去話など


